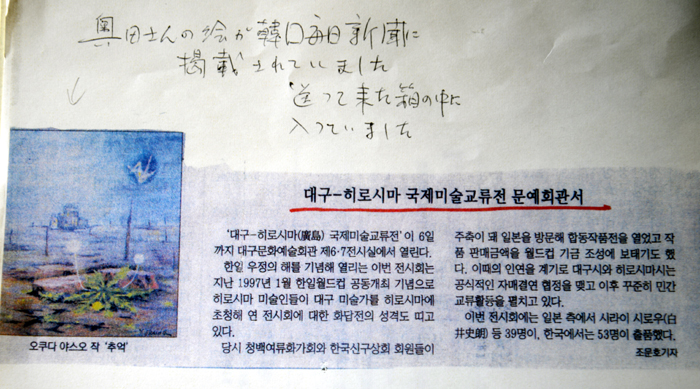物には生命が宿っている。年月に自然に犯され、堪えている
物の哀れさを、追求しつづけたい。
三次市 (旧双三郡)吉舎町
1972年
広島職場美術協会加入(連続出品)
1996年
春陽会初出品
2000年
国民文化祭(ひろしま) 佳作
2004年
奥田康夫ふるさと展(あーとあい・きさ美術館)
2011年
ギャラリー宮郷 個展
ASAギャラリー5人展
2013年
ヨコタギャラリー 3人展
現在
春陽会会友
廿日市美術協会会員
http://www.shunyo-kai.or.jp/lists/461.htm
春陽会 のページでも氏の作品を見ることができる。
■生命の営みに哀を見る
アトリエには廿日市市の美術を担う仲間がよく集まるそうだ。5、6人のマイコップが置いてあるほど。氏の気質があらわれた気の置けない空間は、居心地がよすぎ、つい皆があつまってしまうのだと思う。訪ねて行ったのは4月の半ば。来る春陽展はすでに送り、今平和展出品のために新作を描かれていた。コンクリートの剥落した部分の向こうに覗く海。防波堤や錆が浮いたコンクリートの表面などをテーマとして取り組んでおられた。どこで筆をおくか。手をおいて、眺めて。また色をのせる。アトリエのひと隅に、柘榴が一つついた枝が置かれていた。氏は絵の題材としてよく柘榴を描かれたそうだ。透明感のある赤が、寂れた色に変わっていくその過程を幾度も絵にとどめる。赤の色には思い出があると言われた。彼岸花で有名な三次市吉舎町出身とのこと。その中でも馬洗川沿いの栗林が枯れて白い幹と枝ばかりなった時、赤い彼岸花の絨毯とのコントラストが印象的だったそうだ。
■絵画で発露するもの
35歳くらいから職場のクラブで絵を描き職美展に出していた。その頃は大きい企業の、中国放送、中国新聞、旧国鉄、旧電電公社などがこぞって職場で書道や絵画、詩吟の会、山岳部などの活動を奨励し、一緒に働く社員の一体感を育てていたのだ。高度成長期のおわりとともにその活動の規模は小さくなっていった。それに伴い発表の場を大正11年から続く春陽会にもとめ、描き続ける。36年前には廿日市美術協会に入り現在に至っている。
1999年、一か月間イタリアへ行き、ベネチアへは2週間ほど滞在したとのこと。スケッチをしながら移動したが、その当時のイタリアのインフレはものすごく、1000リラが80円ほど。5万円ほど両替したら弁当箱くらいの紙の束が返ってきて目をまるくした。楽しい思い出話を伺い、なるほどスケッチは明るい透明感が印象深い。快活な空気は絵の外に広がっていく。
8年前、大邱市との広島国際美術交流展に出品。氏が描かれたのは、ほのかなパステルの空色を基調に遠景に原爆ドーム、空に小さく折り鶴、近影に咲くたんぽぽ。氏は戦争末期矢賀に住み、原子爆弾の光が見えた一瞬後には、青天井でガラスもない、ほこりが舞う中にいたそうだ。その後、宿舎は避難してきた人々の救護所になり、復興のなか、どのように町を再構成するか模索する時代を生きてきた。当時、焼け野原になった広島には、70年草木も生えないといわれていたそうだが、一年もたたないうちにキョウチクトウなどの花が咲き、人々は元気づけられた。打ちのめされた街を描くより、往事の人々の希望を表現したかったと言われた。
■自然と対峙するものたち
絵画を始めた当時、古いものの材料がここかしこにあり、絵として成り立っていたそうだ。蔵、苔生した家を探して山陰へ行き、ずいぶん描いた。最近は漁港も漁船など、綺麗すぎ描こうという気になれない。壊れていくものは昔から絵の題材にとりあげられてきたが、その根底にあるのは何なんだろうと筆者は不思議に思っていた。氏の描くコンクリートの壁には、人と同じ刻に存在する同胞であるかのようなイメージがある。私たちが、普段接している建築資材としてのコンクリ―トの武骨な粗さ、無機質なつめたさが感じられず、別の側面を観照することができるのだ。数千年にわたる風雨にも耐性があるというローマンコンクリートとは違い、産業革命以後、大量に使われたセメントコンクリートの寿命は短い。
世界各国の近代都市を形づくり、山、海、川などの自然の荒々しさから人々の生活を守ってきたにもかかわらず、あまり顧みられず、数十年でひび割れ、剥落し、錆汁に汚れ、歪む。コンクリートの材料の石灰岩には珊瑚や三葉虫、アンモナイトといった化石が含まれている。人の営みを助けるために再び使われ、都市とともに齢を重ねる。塩害に苦しみ、波にもまれて擦り減っていく防波堤は、人の社会の外骨格。コンクリートには生命を持つもの故の哀しみが、表れているのだそうだ。
アトリエのなか、圧倒的な存在感で100号の大きさにリアルに描かれた防波堤。崩れた穴の遠く、空と海が迎える。静かで温もりを持ち、奥行へ誘導される視線の先に開放がある構成。この包容力と物への共感、そして希望は、ものの哀れに寄せる氏の視線が優しいからなのだと思った。
<文/栗田祥子 ・ 写真/原敏昭>